

典型的な水平壺 (蓋の裏に水平とあります) |
■水平壺というのは,宜興で作られた茶壺の種類の一つで,茶壺の重心が茶壺の中心になるよう,胴体のバランスや,把と注ぎ口の質量を同じにするような設計を行うことで,茶壺を水に浮かべても水平を保つという意味です。 この水平壺,ちょっと調べてみるとそんなに古くから作られていたものでは無いようです。水平壺は,清朝中期から末期にかけて初めて登場し,蓋の裏に水平という字が書かれるようになります。 それ以前には,三平の原則が無いデザインのものや,大きなバケツのような茶壺が主流でした。今でも,宜興では大きな茶壺が中心であり,あまり小さな茶壺というのは作られていません。 現在中国茶を楽しまれている方のほとんどはこの水平壺というのを一つはお持ちだと思います。大体両手に包めるような大きさで,かつ,把,注ぎ口を水平に揃えている宜興茶壺は,究極の美しさを保っています。 |
| 水平壺の誕生(私見) | ||||
| ■宜興茶壺の始まり 固形茶から葉茶による淹茶の習慣が始まった明代には,茶器は金属のものが一番良いと書かれています。 一方宜興という窯は,越窯の流れを汲むもので,宋代から青磁を焼いていました。また宜興は固形茶の頃からお茶の名産地でもありました。宜興は,この淹茶の登場とともに,明代中期には急須を作るようになります。当然ながら,この金属製が一番という評価によって,最初に作られた宜興紫砂の茶壺は,大ぶりの金属製の注水器を模したものでした。 その後,武夷岩茶等良質な葉茶が出現し,茶葉自体の改良が行われ,その結果,岩茶などのえぐみを抜くには宜興紫砂が一番であるという評価を得るようになります。しかしながら,明代の出土品をみると皆,やかんのように大きなものが多く,時大彬のものが小さい茶壺を始めたと行っても,水平壺のような2〜3杯壺まで小さいものはありません。 では手のひらで包めるような大きさの水平壺とは一体いつからあるものなのかというと,これはやはり福建,潮州あたりで始まった工夫茶の発展と結びつくと思います。一般的に,宜興より北には,大ぶりの茶壺が出荷され,小さな急須は福建,潮州,日本,タイなどに出荷されました。 |
宜興陶瓷博物館蔵の初期紫砂 (かなり大ぶり) |
|||
現代潮州の茶館 (小さな孟臣壺で淹れる) |
■水平壺と工夫茶 正確な資料が見つからず潮州あたりでいつ頃から工夫茶が始まったのかは定かではないのですが,潮州では宋の時代には小杯茶という,小さなぐいのみでお茶を飲む習慣があったそうです。 また,潮州にはいかにおいしくお茶が入るかを競う闘茶の習慣があり,明代には「茶注は小さいものがよい。大きすぎるのは良くない。小さいと香気が残るが,大きいと散りやすい。一人で飲むなら小さければ小さい程良い。」(茶疏:ちゃそ)と書かれ,清朝始めにはこれらの工夫の展開として,ごく少量のお湯で比較的大量の茶葉を使って淹れる工夫茶の原型が始まったようです。 茶舟を使う現在のような工夫茶は清朝中期頃には確立されたようで,これに見合う茶器として宜興では清朝中期から末期にかけて蓋の裏に水平という言葉を入れた,水平壺が作られるようになったようです。 工夫茶の書物で,急須は「孟臣缶」でなければならないという有名な文言があります。これは明代の作家である恵孟臣がすでに小さい茶壺を作っており,これが工夫茶に一番適しているという意味であると思います。ただしこれをもって明代に,工夫茶の道具として恵孟臣が水平壺を作っていたのかどうかは資料上では確認出来ません。ご承知のように恵孟臣というのは,現在もたくさん作られていますから,一番真贋がわからない作家の一人だからです。現在のところ広東省の明代の墓から副葬品として出土した孟臣壺は本物であろうと考えられていますが,それは非常に大きなもので,工夫茶用の小さなものではありません。小さい茶壺イコール水平壺とはどうもいえないような気がします。水平壺を孟臣が作っていたかはともかく,小さい茶壺を孟臣が作ったというのは本当のことであるかもしれません。 |
|||
| ■日本における小さい茶壺のニーズ 日本では信長の頃から抹茶道を半ば政治的に伝承してきましたから,天目茶碗などの道具が中国で作られなくなり,茶道具の主体が抹茶茶碗から急須になっていっても,これを受け入れることはせず,福建やベトナムなどの粗悪な茶碗を「わび」「さび」などといって,珍重しており,日本に急須が入ってくるのは煎茶が普及しだしてから以降でかなり遅くなってからであったようです。 従って,日本では宜興黎明期の大きな茶壺の伝世品というのは,ごく限られており,宜興の伝世品としては万福寺に伝わる,隠元和尚の茶壺くらいではないでしょうか。隠元和尚の茶壺は万福寺に今でも残っていますが,これは一つは小さいバケツほどの大きさ,もう一つも水平壺からすればかなり大きめのものです。大きなものは,倣大彬という字が彫られており,当時の宜興では普段使いのものであったと思われます。 江戸中期くらいから,中国文化文物に対して非常にあこがれを持っており,一部大阪の数寄者の間から淹茶が始まり,これが煎茶の始まりとなります。当時,唐物の茶道具はどんなものでも珍重されていたようです。また,1500年の終わりに京都で玉露が作られるようになり,たくさんの茶葉を使い,数滴の甘露を味わうという煎茶のニーズから,宜興に小さい茶壺をオーダーしたものと思います。 この日本の煎茶道具は,潮州の流れをくむ福建あたりの道具の影響を受けています。ボーフラと呼ばれる素焼きの湯沸かし器や涼炉などは,当時の福建省でおそらくお粥とか漢方薬などを煎じるために使われていたもので,これが煎茶道具の最上位に格付けられていることからも伺いしれます。 というのも江戸初期から始まった贅沢禁止令と鎖国の影響で,長崎出島に限って来ていた清人達のほとんどが福建の人間だったことから,福建の工夫茶の習慣が日本に入ってきたのでは無いかと思います。ただし,清朝の焼き物はとんでもなく高価で,一般の普段使いの道具として一般の人間が買えるようなものではなかったようです。 江戸末期から明治にかけて,煎茶がブームになり小さな茶壺を大量に宜興にオーダーするようになったと思われます。 日本でも,急須にお湯をかける手前がありますが,一般的には,急須にあふれるほどのお湯をいれませんから,小さい茶壺は必須であっても,水に浮く水平壺である必要は必ずしもなかったと思われます。 |
江戸末期の煎茶道具 (大きな茶壺は水注(水差し)として使われた) |
|||
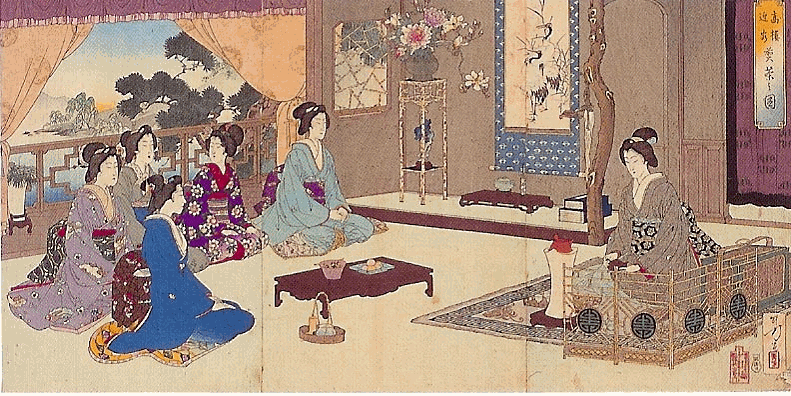 当時の煎茶ブームを伝える浮世絵(右の女性の手に宜興茶壺があります) |
||||
|
■タイ王朝のニーズと工夫茶セットから見た水平壺 もう一つ宜興には,大規模なマーケットがあります。それはタイです。タイ王朝はそのルーツに潮州系の華僑の血が入っていると言うことで,潮州のお茶の習慣,つまり工夫茶と,その道具が昔から使われていました。 今でも,バンコックのナショナルミュージアムには,たくさんの工夫茶セットが展示されています。 それにしても,水に浮いても傾かない水平壺というのはなぜ生まれたのかはずっと疑問に思っていました。水見浮いても傾かないと言うからには,水に浮かすような手前があったということですが,現在の工夫茶を見ている限り水に浮かすような入れ方はありません。 清朝時期の潮州工夫茶の写真などを見たことが無いので,小さい茶壺から水平壺への展開の理由がよくわからなかったのですが,これがタイの工夫茶セットから想像できます。 左の写真がそうですが,茶舟に注目してください。本当に背が高く,ここにお湯をなみなみと入れたら水平壺でなければ,傾いてしまうと思われることです。つまりタイの工夫茶がこのようなものであったとすると,本家潮州でも茶舟は同じように背が高く,単に小さい茶壺ではなく水に浮くバランスを持った水平壺でなければ,工夫茶の道具にはならなかったのではないかと想像できます。 おもしろいのは,蓋碗が茶海として使われていることで,今では潮州では蓋碗に直接茶葉を入れて茶杯に注ぎ分けたりしますから,清朝中期から末期をピークにして,だんだんと工夫茶自体も簡素化されてきたのではないかと思います。従って,現在の宜興紫砂には水平の文字が入っているものはありません。 それには,茶葉自体の品質向上も大きいと思います。最近の台湾茶特に梨山などを飲んでいると,紫砂のようなえぐみを取るという性質は,洗茶と同様にだんだんと必要なくなり,お茶の品質を100%出せる磁器製のものの方が良くなっていくのではないかと思います。むしろ,茶道具としての美という観点から宜興紫砂は残っていくのではないでしょうか。 |
|||
| ■ヨーロッパ ヨーロッパも大量の宜興製品を輸入していますが,これは大きなものも小さなものもあります。紅茶のニーズからは小さな茶壺が必須ではなかったようです。 ■ 中近東 中近東は,元の時代から景徳鎮や龍泉窯の焼き物を大量にオーダーしていますが,紅茶というよりターキッシュコーヒーなどが主体のこの地域では,淹茶の習慣が無く,従って宜興茶壺しかも水平壺を使うニーズは無かったようです。 |
宜興紫砂の市場 |
|||
タイ国立博物館の図録,愛知陶磁資料館,板橋区立郷土資料館の資料などを参考にさせていただきました。